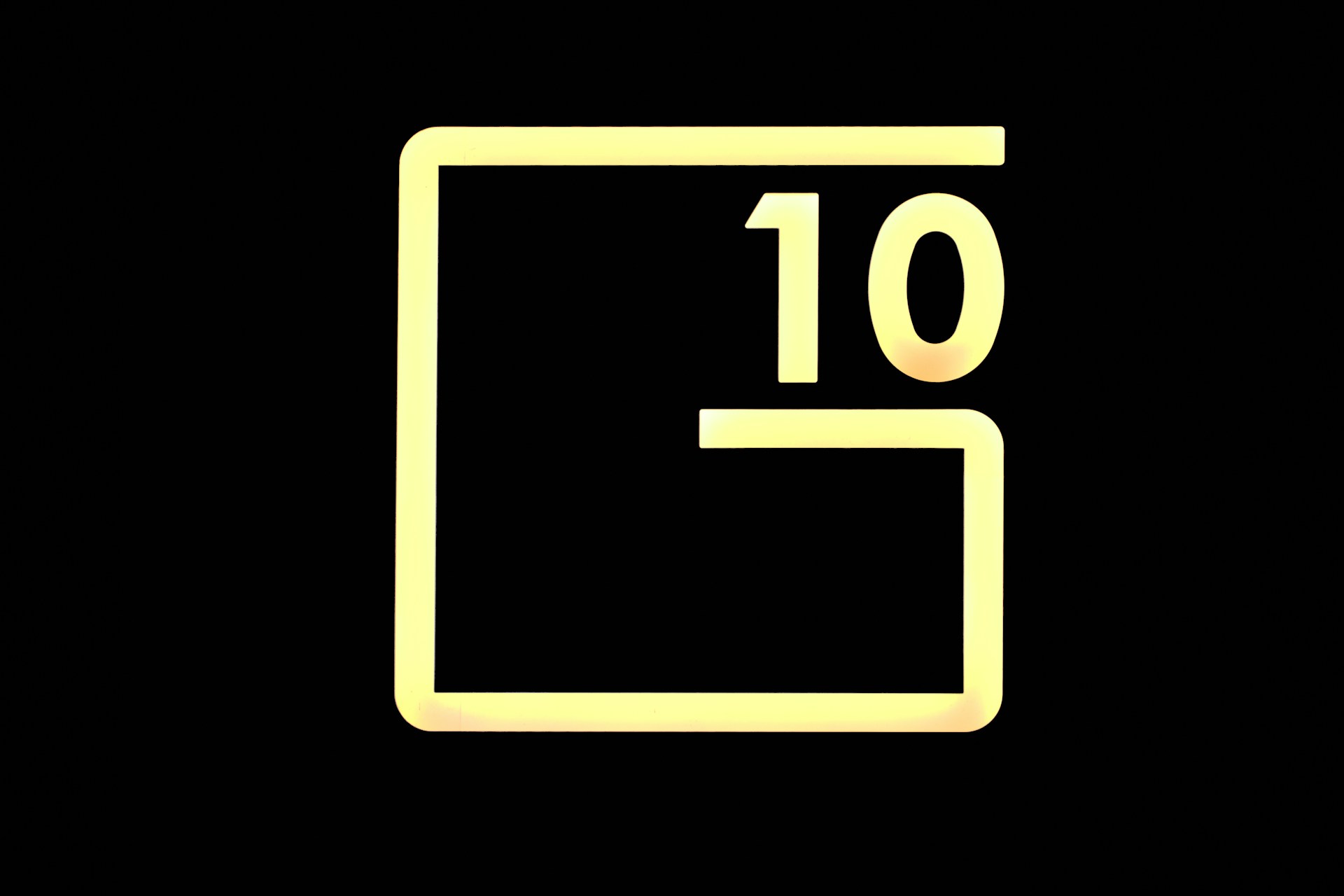
こんにちは、杉崎(@web_norcs)です。
ブログを始めようとしたときに、多くの人が最初にぶつかる壁は「どのジャンルで書くか」です。
間違いなく万人共通の悩みですね。
ここを適当に決めてしまうと、3か月後には更新が止まってしまうし、どれだけ頑張っても集客や売上にはつながりません。
ジャンルの選び方ひとつで、あなたのブログが「ただの日記」で終わるか「仕事を呼び込む営業マン」になるかが決まるということです。
ジャンル選びは
「好き・得意」だけでは足りない
ジャンル選びに際しては、あなたが「好き」または「得意」な分野から選ぶようにしましょう。
整体師なら「肩こりを悪化させるNG習慣」、美容師なら「40代に似合うショートカットのポイント」など、日常でお客さんに伝えている知識をそのまま記事にできますから、更新も楽です。
しかも、他の人には真似できない現場のリアルを綴るからこそ、読者は「やっぱりプロの言葉は違う」と信頼してくれる。
好きや得意をベースにすれば、苦にならずに記事を書けるのは大きな強みですよね。
実際、継続できるかどうかはこの「苦にならない」という感覚に大きく左右されるので、だからこそ、まずは自分が書きやすい領域から入ることは大正解なんです。
ただ、好きや得意だけでは不十分でして(テンション下がるようなこと言ってごめんなさい)。。
どれだけ自分が熱中できるテーマでも、それを求める人がいなければ「自己満足の記事」で終わってしまうからです。
趣味ブログとして楽しむならそれでもいいのですが、仕事や集客につなげたいのであれば、相手の関心に寄り添う視点が欠かせません。
「自分が書きたいこと」と「人が知りたいこと」は必ずしも一致しないという現実を、まずは頭に叩き込んでください。
読まれるためには
需要の軸が欠かせない
あなたがどれだけ情熱を持って書いても、世の中の人が求めていなければ、残念ながら読まれません(ここめちゃくちゃ大事)。
例えば、整体師が「骨盤矯正の奥深い理論」について何千字も熱を込めて書いたとします。
専門家としては素晴らしい記事ですが、一般の人は「骨盤矯正の理論」なんて検索しません。
彼らが調べるのは「骨盤矯正 効果 いつから」や「産後 骨盤矯正 行くべき?」といった日常的な悩みに直結する言葉です。
つまり、ニーズに沿わなければどれだけ丁寧に書いても読んでもらえないんですよ。
他に、美容師もそうですね。
毎日カラー剤や髪質改善についての専門的な話を熱弁したくなるかもしれません。
が、読者が気になっているのは「白髪をどう隠すか」「朝の寝ぐせを3分で直す方法」「40代に似合う髪型」など、生活に直結するテーマ。
いくら「最新のカラー理論」を語っても、それは同業者しか興味を持たない内容で、お客さんは振り向いてくれないのです(ターゲットによりますが)。
需要のあるテーマに合わせなければ、専門的な記事は「誰の目にも届かない独り言」になってしまうんですよね。
これは、自分の情熱や専門性を否定するのではなく、「読者がどんな言葉で調べているか」に変換することが必要だということです。
マーケットのニーズに寄せるだけで、同じ知識でも「必要としている人」に届き、信頼や仕事につながりますので、この点は忘れないようにしてください。
「好き」と「需要」の
交わる場所を探そう
理想は、この二つが重なるポイントを見つけること。
「好き・得意」だけでは独りよがりになり、需要だけでは息切れしますから、だからこそ掛け合わせが重要なわけです。
- 整体師なら「デスクワークで腰痛に悩む個人事業主向けのケア方法」
- 美容師なら「忙しい子育てママでも3分でできるヘアアレンジ」
といった具合に、無理なく書けて、しかも読者に刺さるテーマを見つけて記事を書いていってください。
もしここを意識せずに始めてしまったら、間違いなく途中で筆が止まり、成果も出ずに「やっぱりブログは向いてなかった」となってしまいます。
逆にこの掛け合わせを掴んだ人だけが、仕事につながる発信を続けられるということです。
考えすぎずにまず10記事出すこと
大切なのは、いきなり完璧なジャンルを決めようとしないことです。
最初から「これ一本で一生やっていく!」と決め打ちする必要はありません。
むしろ、最初は「自分が書きやすいテーマ」や「お客さんからよく聞かれる質問」から始めてみることが正解です。
「腰痛 ストレッチ」について書き始めてみてもいいし、「毎朝5分でできるヘアケア法」でもいい。
まずは発信してみることで、読者がどんな反応をするのか・検索されやすいのかが見えてきますから。
そこから少しずつ方向性を修正していけばいいんですよ。
考えすぎて手が止まる人があまりに多いんですが、やめてくださいね。
まず記事を世に出すことが大切なんです。キーワード調査や戦略はもちろん必要ですが、机上で悩んでいるだけでは何も始まりません。書かないと文章は上手くならないし、何がウケるのかもわからない。
とにかく出してください(しつこい)。
記事を公開するたびに反応がデータとして返ってくるので、その積み重ねこそが、進むべき道を教えてくれます。
つまりジャンル選びは、最初に大きな覚悟を決めるものではなく、走りながら研ぎ澄ませていくもの。
怖がらずにまずは一歩を踏み出すことが「仕事につながるブログ」への最短ルートになります。
まずは10記事書いてみましょう。話はそれからです。


コメント